「わたしねぇ、もしかしたら詩人になりたかったのかもしれない」
アイスカフェラテの氷をストローでかき混ぜながら、スナさんはそう言った。向かいに座ってタルトをつついていた私は、はあ、と返事をして、「詩人ですか」とその耳慣れない単語を復唱した。
「そう。詩人」
スナさんがくり返すのを聞きながら私はタルトを口に運ぶ。たっぷりの苺があしらわれた「季節の果物のタルト」は、今日で販売が終了になるらしかった。明日からは「メロンのパフェ」が始まると壁に貼ったチラシに書かれている。
右手側の大きな窓から見える緑はいつのまにか深く、濃いものになっていた。新緑のあいだから五月の光がこぼれて、丸いテーブルの上に葉影が揺れる。
桜の季節が終わって、新緑の時期がきて、やがて夏が来る。そんな日の昼下がりである。スナさんとは久しぶりに会った。あちらから突然に連絡を寄越したのだった。
ラインに設定しているスナさんのアイコンがスマホの画面に現れたとき、咄嗟に誰だったかわからなかった(その時、私は自分がとても薄情な人間に思えた)。スナさんはラインの名前を“s”と表記していて、わかりにくさに拍車をかけた。でも、「元気?」とひとこと、吹き出しの中にぽつんと置かれているその言葉で、すぐにこれはスナさんだとわかった。私に「元気?」などと優しい言葉をかけてくれる友人はスナさん以外に一人もいなかった。
スナさんと会うことに決めたのは、さみしかったせいもあった。私は五年ほど一緒にいたパートナーと別れたばかりだった。自分で決めたことなのに、胸にぽっかり穴が空いたようで、とても、とてもさみしかった。しがないwebライターとして仕事はほそぼそと続けていたけれど、ぜんぜん売れっ子じゃないし空き時間はそれなりにあった。休みも取ろうと思えばいくらでも取れた。それに比例して無論、稼げる額は変わってくるのだけれど。
それで、連休のあいだに忍んでいる平日のいちにちを選んで、スナさんとお茶をすることにした。連休直撃だと絶対混むから外出したくなかった。その価値観はスナさんと一致していた。平日がいいよね、祝日はいやだよね、土日も混むよなあ、などのやりとりを何度か交わした。
ストローの首の部分――鳥の首から嘴にかけての輪郭に似ている――をつまむスナさんの指は、ネイルもなにもほどこされていないのにとてもきれいだった。線が細くて、指先にかけてすっきりとしたかたちをなしている。
指に限らずスナさんはうつくしい人だった。男性のようにも、女性のようにも見える外見で、野鳥がひそやかに囀る程度のヴォリウムでしゃべる。声は中性的な、心地好いアルト。
都会の雑多な駅の中で待ち合わせをしていても、スナさんの周りだけ発光しているように見えるからすぐにわかる。都会の駅でスナさんと待ち合わせをしたことなどないのだったけれど。
「詩人ってなんですか」
タルトを咀嚼して飲みこんだ後、吐き出された私の息は甘かった。コーヒーのマグを両手で包んで、スナさんの目を見た。スナさんもまた私の目を見つめ返した。
私の問いに、スナさんは「そうだねぇ」とうすく笑った。
「依ちゃんってさらっとむつかしいことを訊くよね」
「だって、私、詩がなんなのかもよくわからないから」
へえ、とスナさんは言った。感心したように。
「ぜんぜん、読まないの、詩」
「読まない。ぜんぜん」
私の返答に、でもスナさんは絶望的な顔をするわけでもなく、だめだコイツと呆れるでもなく、いつも通りのクールなようすでアイスカフェラテを啜った。くち紅の塗っていない唇が尖って、セクシーだった。
スナさんは頬杖をついた。
「詩人か。……詩人ってなんだろうか? そんなこと、考えたことなかったな」
え? と私は目を丸くした。
「考えたこと、ないの」
それなのに、あなたは詩人になりたかったの。なりたいの。そういうことって、あるの。
畳み掛けるように質問した。スナさんははらはらと笑った。
スナさんの、葉っぱがふるい落とされるような笑い方が私はすきだった。はらはらと、スナさんは笑うのだ。はらはら、はらはらと。
「考えたこと、ない」
はっきりとした口調だった。私は、はあ、と思った。コーヒーをひと口、飲んだ。とても渋くて苦い味が、舌いっぱいに広がった。
なりたい職業について、それが「何」なのか考えたこともないというのはとても不思議で理解し難いことだった。就職の際に「この仕事(詩人)の魅力を語ってください」とか言われたら終わりだ。でも詩人の人にそんな問いかけをする人なんているだろうかしら。
詩人って、わたしの思う詩人って、もっと、実体がなくてふわふわとして、掴めないかたちをしている、気がした。
言葉にできないから「詩人」なのかもしれなかった。わたしの問いかけもそもそもにして野暮だ。スナさんはきっと正しくて、詩人が何かなんて考えたこともない、というのがつまり答えなのだと思った。
「わたしはことばがすきでしょう」
スナさんは静かに静かに言葉を重ねた。私は頷いた。そう、スナさんはことばをとても丁寧にあつかう人だった。
「それで、詩人はことばを使う仕事をするでしょう」
「そうだね、うん……。きっとそう。よく、わかんないけど」
「だから、そういうものなのだと思うんだよね、詩人って」
わかんないんだけれどね、とスナさんは舌を出した。可愛らしいほほ笑みだった。スナさんはたまに、こういう、少女みたいな笑い方を自然にする。見ていてちょっとドキッとしちゃうような、でも狙ってやっていないとわかる、キュートすぎる仕草。
「ことばをあつかう人になりたかったんだよね。それで、だからたぶん詩人だったんだ」
依ちゃんは文章を書いてくらしているから、もうすでに詩人だね。スナさんはそう言って、カフェラテを吸い上げた。そんなことはないでしょうよと私は思ったけれど、詩人と言われて悪い気はしなかった。私は黙って肩をすくめた。
会計は別々にしてもらって、レジでコーヒーとタルト分のお金を払った。スナさんは小銭入れから五〇〇円玉と五十円玉を出してトレイに載せた。がま口の小銭入れはいつかどこかの蚤の市で見つけて、スナさんに似合いそうだと思ってお土産に私が購入したものだった。あれは何年前のことだっただろうか。忘れてしまった。
「スナさんのそれ、私があげたやつだ」
カフェを出て、トートバッグに小銭入れをしまったスナさんに私はぼそっと言った。ああ、とスナさんは笑った。
「そうそう。三年も前になるね。ずっと使ってる。依ちゃん、ありがとうね」
そうだったっけ。三年も前のことだったっけ。三年のあいだに世の中は電子マネー電子決済新しい生活様式へと時代は移り変わっていって、現金を持ち歩く人が大幅に減った。小銭入れなんて時代錯誤も甚だしい――私が自分であげておいてなんだけど――それをまだまだ現役で使ってくれているなんて、そこからカフェ代を支払っているなんて。
「スナさんって、ほんとうにスナさんですね」
おかしかった。スナさんもまた、はらはらと笑った。
「たぶん、そういうことなんだと思う」
うん、と私は頷いた。そうだと思う。そういうことなんだと、思う。
「スナさんは、詩人ですよ。私なんかよりはるかに」
私が言うと、スナさんは困ったような顔をした。
「そうかな。そうだったら嬉しいのだけれど」
そうして、ありがとう、と言った。
あなたが詩人じゃなかったら、誰が詩人なんだい。スナさんの弱々しい笑みを見て、私は、強く言及したい気持ちだった。
余計には突っ込まなかったけれど、私はスナさんは詩人だとわかっていた。たぶんそれは、出会ったころからとっくに知っていた。
スナさんと出会ったのがいつだったのか、それすら私は忘れてしまった。スナさんはおぼえていると思う。紙の日記に、当時の状況を淡々と書き記していると思った。だからもうスナさんは詩人なんだ。
「今も、なにか書いてるんですか」
歩き出しながら訊ねる。うん、とスナさんは頷いた。
「書かないと、生きていかれない」
一歩を踏み出すたびに、葉擦れの音が聞こえた。つま先にかげが揺れる。
私より背の高いスナさんは真っすぐに道の向こうを見ている。木立が左右に生い茂った道。舗装されていない土の道は歩きにくい。スニーカーの底で砂つぶと小石がじゃりじゃりと音を鳴らした。
スナさん、と私は言いたかった。
ずっと、書いていてくださいね。書かなきゃ生きていかれないあなたが、いつか書くのをやめてしまう瞬間を、私は見たくないので。
私たちのくらす田舎のまちの空は、澄んでいてとても、とても広く、青かった。小洒落た駅ビルのない世界で私たちはくらしている。高い建物がないから視界はいくらでもひらけていて、空が見えて、道を歩いていると近所のおばあちゃんとすれ違う。田畠がたくさんある。むしろ田畠しかない。そんな愛くるしくてせつないまち。
じゃあ、と、いつもの場所で私たちは別れる。電信柱が左右の道の選択肢のように立つそこで、片手をあげて、スナさんは私を見送ってくれる。いつも。
細身で背の高いスナさんの、きれいな体のラインにさみしさをおぼえた。手を振って、何度もスナさんを見返しながら、私は私のアパートへの道を歩きだす。またね、とスナさんが言ったので、私たちはたぶんまた、近々会ってお茶をする。その時にスナさんは、依ちゃんわたし詩人になったよと胸を張っているだろうか。未来のことは誰にもわからないし私にもそんな能力はないから、どうなるかなんてわからない、知らない。私は連休中に片づけてしまいたい仕事について、すでに考え始めている。連休中は家で仕事をして、世の中の連休が終わったら遊ぼうと、四月に入った時分から決めていた。そんな私は絶対に詩人じゃないよな、と一人でくすくす笑った。
スナさんはまだ手を振っていた。ばいばい。私も手を振り返した。それから前を見て、スナさんの視線を感じながら、でももうふり返らなかった。

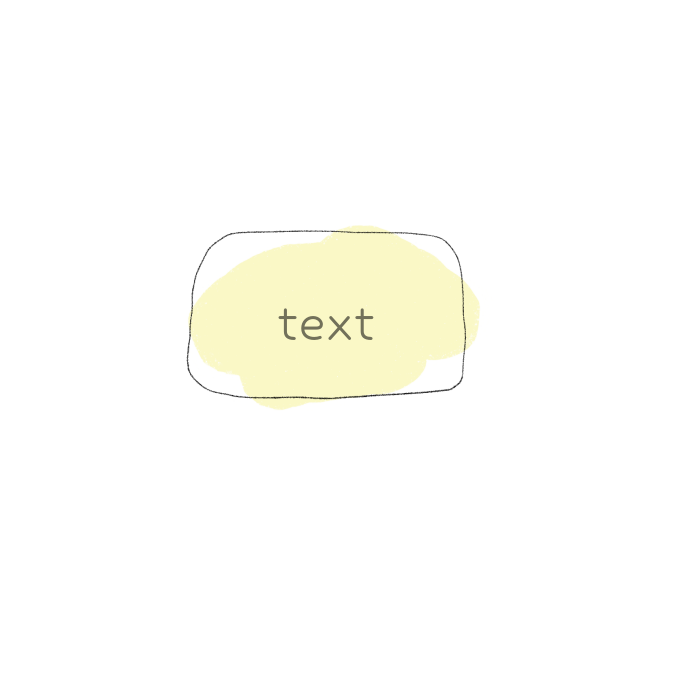
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます