あの人の車の中は、あの人の“ナカ”ってかんじがして、いれば心地好い。シートの振動が背中を伝う、地道でまっとうな響きだ。車内の空気はあたたかく濁り、どこにもゆけずに停滞していた。振動も、空気も、オーディオからこぼれるロバート・プラントの歌声も、あの人の“ナカ”にふさわしく、存在する。
「いいうた」
私がいうのに、あの人は温厚そうな横顔を晒して、黙っている。私の意見に感想に、否定も賛同もしないのはあの人の癖で、習い性で、処世術なのだと最近になってようやく理解した。私はその横顔――とがった鷲鼻のライン、唇の作る影など――を見やって、あの人の感情を勝手に想像する。自分の都合のよいように、解釈する。
日暮れの道路は閑散として、つめたい景色がフロントガラスの向こうに拡がっていた。10月の長雨がしとしとと、街を、路を、ひやしていて、私たちはぬくい空気にからだをひたして、まるで他人事のようにそれらを見つめている。
既視感のようなものが、あった。私はいまのこのかんじを知っている。いま、見ている景色を知っている。このにおいを、空気を、つめたさを、知っている。
それをいつどこで知ったのかを考えるけれど、思考は暖房のあたたかさに溶かされ、とろとろとした疲労が全身にめぐるのをいたずらに感じるだけだった。
「天国への階段」
ふいに、あの人が呟いた。「ギターやる人が、最初に練習する入門曲だよ」
「……あなたも、したの?」
「したよ」
「弾けるのこれ」
声がとぎれ、せつなげなギターソロにうつった。ジミ・ペイジの紡ぐ正確な音で車内がみたされる。
「弾けるよ」
あの人はおだやかに笑った。影が頬に皺をこしらえるのを、私は助手席に坐った心細い立場で、ただぼんやりと眺めた。
まだ少年だった頃のあの人のことを、空想する。丈の短い学ラン、だぼだぼのズボンで煙草をくわえ、ギターを抱えて学校の、寒々しい体育館で仲間とうたうあの人のことを、私は写真でしか知らない。写真は声も音も発しないし、けれど彼らの紡いだへたくそな音の塊り、その頃に抱えていたのであろう空気の質量なんかは想像するにたやすかった。頭に思い描けばそれは愛しく、永遠で、ぜったいのもので、もう二度と手には入らない。
ジミ・ペイジのギター・ソロは完璧で、優しかった。完璧に完成された優しさで構築されていた。目の前にいるこの人が永遠に憧れた、なまみの恰好よさとやらが、オーディオからあふれて、あふれて、あふれる。
すごいね、と私は言った。横顔が夕闇に溶けてゆく。鷲鼻も、薄い唇も、瘠せて浮いた頬骨も、夜の色に染まってゆく。私の意見に感想に、否定も賛同もしないのはあの人の癖で、習い性で、処世術なのだと最近になってようやく理解した。
あの人の思いなどすこしも計れないことが歯痒い。鎖されたくちからもう言葉が出ないことを私は知っている。それだから言わんとしているものごとを空想し、自分の都合のよいように解釈して、胸にすとん、と落とすばかりなのだ。
14.1013

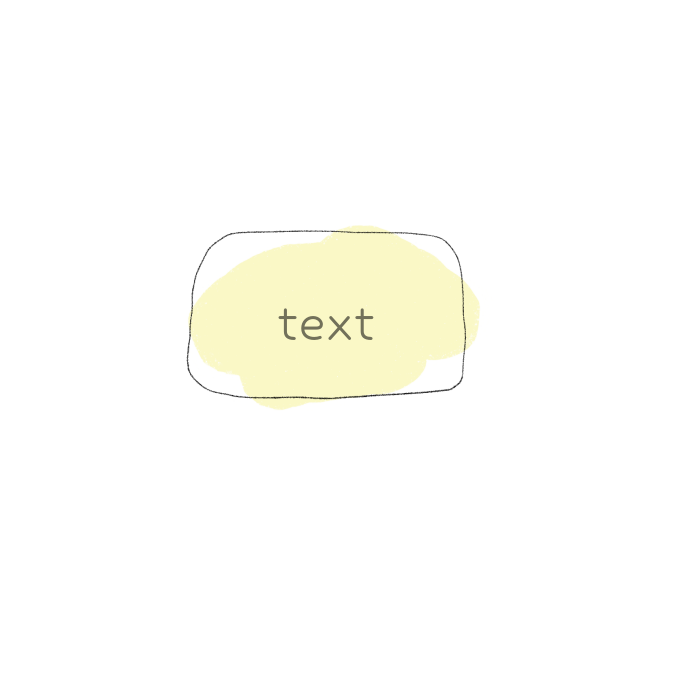
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます